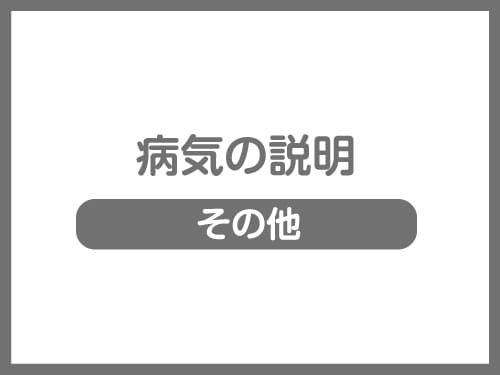
肥満度の目安としてのBMIは、かなり市民権を得ていると感じますが、筋肉質な人を肥満や過体重に分類してしまったり、BMIが正常でも、体脂肪率が高い正常体重肥満を見逃してしまうということもあります。
BMIと体脂肪率のどちらが、死亡リスクの予測に有用化の検討結果がオンライン版のAnnls of Family Medicineに掲載されました。
予想通り、体脂肪率の方が、若年成人における長期的な死亡リスクと高い関連があることが示唆されたとなっていました。
米国フロリダ大学の研究結果ですから、データは私達日本人には流用できないと思います。
ですから、その中身のお話をすることより、それぞれの測定値を絶対視しないで、参考値としてみるというスタンスも必要だということを、書きたいと思います。
BMIは身長÷体重÷体重 というかなりはっきりした数字のデータですから、客観性はあると思います。
ただ体脂肪率は測定の仕方は各種あり、この論文で採用されているのは、生体電気インピーダンス法となっていますから、体重計で測定できる割とお手軽な方法です。
この測定法は、精度は高いとはいえず、水分量 運動 食事によって数値がぶれやすい というのが注意点として挙げられています。
足や手から微弱電流を流し、電気の通りやすさで脂肪量を推定するそうです。
一方精度の一番高いのは、デキサ法といわれるX線吸収測定法といわれるもので、医療機関やスポーツ科学施設などで使われるもので、体脂肪 筋肉 骨密度を部位別に詳しく測定できるそうです。
ただし費用が高く、放射線を微量使う。
ですから、体脂肪率は大切な指標ですが、体重計で測る程度では、正確なところはわからないというのが、ジレンマです。
結局のところ、肉体は、自分の食べたり飲んだりしたものの結果ですから、体内の脂肪のつき具合は、CT等で透視しないとわからないですが、それより日々の食生活を振り返ることで予想する方が意味があるように、思います。





