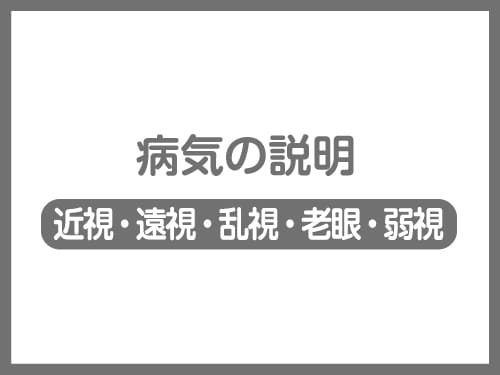
近視の人が多い我が国においては、コンタクトレンズや眼鏡は必需品 という方は多いと思います。
眼科で作成する人もいますが、眼鏡店やコンタクトショップで作成する人も多いでしょうし、何なら雑貨屋さんでもカラコンを販売しているのを見かけることもあります。
その違いはどこにあるのですか と患者さん自身から聞かれることもありますが、私自身は眼鏡店の内情は詳しく知らないので、正直よくわかりません。
眼鏡店でもこの道一筋 というような方もおられるでしょうし、即席で教わった担当者が検査をする場合もあるでしょう。
ただコンタクトレンズの営業担当者が、所属変更のご挨拶に来られた時に、話してくれたことで意外だと感じたことがあります。
それは、今まで医療機関の担当だったけれど、次は商業施設に入っているいわゆるコンタクトショップの担当になり、昇進になる と嬉しそうに教えてくれたことです。
勝手に私としては、医療機関担当の方が昇進ではないかと考えていたのですが、ご本人によりますと、売上高も全然違うし、中途半端な(はっきりそう言われたわけではないですが、単刀直入に言うとということですが)アカデミズムも不要なので、純粋な営業活動としては、大口の顧客の方を、会社は重用している ということが伝わってきました。
コンタクトレンズは、高度管理医療機器クラスⅢに分類されており、販売も許可制で、販売管理者の設置が必要とされていますので、私達眼科医もそのためのレクチャーを受ける義務が課せられています。
でも大きな販売会社においては、そういったことをクリアーするのは簡単なことなのだと思います。
逆に眼鏡の制作にもし全員が眼科医を受診しなければならないことになったら、クリニックは混乱に陥ることは目に見えています。
こういう玉虫色の規制というのも、他の分野でも多くあるのでしょうか。
少なくとも私は、何かトラブルがあれば、コンタクトショップではなく、必ず眼科を受診してほしいと思います。
先程の営業担当者が所属していた会社は、今後は営業担当はクリニックを訪問せず、WEBやメール対応ということです。
そういえばもう何年も前に、外資系の別のコンタクトレンズ会社は、同様の対応となっています。
両社とも外資系ですが、そもそも営業担当者の意義ということを自己否定しているようで、面白いことですが、正直タイミングによっては、煩わしいこともあるので、合理的ともいえるでしょう。
かの営業担当者は、熱心でいい方だったので、昇進を喜んでいたのですが、全員がそういうことになるなら、ちょっとがっかりしているかもしれませんね。





