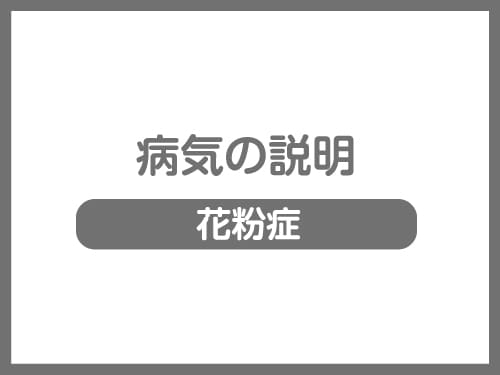
日本気象協会の来春の予想第1報は、9/30に発表され、そのことは先日このブログで簡単にご紹介しました。
過去10年間の平均を例年と呼びますが、宮の前眼科のある伊丹市を含む近畿地方は、予想によると例年比は100% 前年比は80%とやや少ない となっていました。
つまりおおよそ平均的な飛散量でしょうということです。
ところが花粉症は、気象条件の影響を大きく受けるため、地域によって大きく異なります。
例えば、昨年の飛散が少なかった北海道 東北地方は、どちらも非常に多いとなっており、東北地方の前シーズン比は730% 例年比200% 北海道は前シーズン比 420% 例年比250%
一方近畿地方を始め、西日本はほとんどの地域で、例年比100% 昨年比は、去年は飛散量が多かった地域が多いため、四国を除いて60~80%となっており安心していました。
ところが、参天製薬のサイトの11/5のニュースに、来年の花粉の飛散傾向というのが載っていたので、気象協会の第2報は、12月初旬と聞いていたのに、早まったのかと、のぞいてみました。
それによると、大量飛散の目安となる2000個/㎠となる地点は55/57 札幌市 宮崎市以外の地点で2000個/㎠以上 飛散開始日は平年並み という大見出し。
これを読んだ印象としては、来年も全国的に多い に変化してしまったのか まずその2000個というのがどれ位多いのか見てみたところ、花粉学会というのがあり、2024年から花粉情報の新基準ができたことが分かりました。
花粉数(1㎠あたり)50~100未満を非常に多い 100個以上をきわめて多い と呼ぶことが決まったとのこと。
飛散情報を出す判断基準として、こういう改定をしないと、飛散開始前に15%前後の患者さんが発症していたことによるようです。
ですから花粉症の始まりを告げる数字としては、学会としては、30~50未満を多いと認定しているとのことです。
花粉学会によると、この30年間で花粉数が2倍以上に増加した地点が多く、全ての観測点で2000個以上になり5000個を超える地点が増加したとのこと。
そうするとほとんどの地域で、大量飛散というこの文言は、花粉の季節がやってきたという自然現象を伝えていることと理解した方がいいのかもしれません。
監修はNPO花粉情報協会 となっており、アレグラという抗アレルギー薬をだしている製薬会社の来春予想にも同協会の引用がされており、薬業界においての標準かもしれませんが、気象庁 または日本気象協会のデータの方が正確なように思います。
気象庁は国土交通省の外局 日本気象協会は一般財団法人ですから、民間組織ですが、気象庁のデータを利用しつつ産業や生活に寄与することとなっています。
気象状況と関係の深い産業などもありますから、そういう企業のコンサルティング等も行っているようです。
精度は2024年の検証では、気象庁のデータより誤差が少ないという情報もあります。
随分話が広がってしまいましたが、結局今のところ、近畿地方は去年よりは軽く大体例年通りと思っていて良さそうです。





